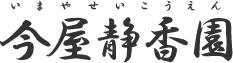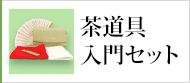【茶器/茶道具 抹茶茶碗】 祇園祭 大船鉾(おおふねほこ) 加藤起楽作
【茶器/茶道具 抹茶茶碗】 祇園祭 大船鉾(おおふねほこ) 加藤起楽作
商品コード: tyawann-1397
受取状況を読み込めませんでした
●祇園祭(ぎおんまつり)…京都市東山区の八坂神社(祇園社)の祭礼で、明治までは「祇園御霊会(御霊会)」と呼ばれた。
7月1日から1か月間にわたって行われる長い祭である。
祭行事は八坂神社が主催するものと、山鉾町が主催するものに大別される。一般的には山鉾町が主催する行事が「祇園祭」と認識されることが多い。
その中の山鉾行事だけが重要無形民俗文化財に指定されている。
●大船鉾(おおふねほこ)とは…祇園祭の山鉾の一つ。
毎年7月24日に行われる後祭で、鬮(くじ)とらずで最後を巡行する。
占出山や船鉾と同じく『日本書紀』の神功皇后(じんぐうこうごう)の新羅出船に由来する。
前祭の船鉾が「出陣」を表すのに対し、後祭の大船鉾は戦を終えて戻る「凱旋」の場面を表す。
応仁の乱以前から存在する歴史の古い鉾で、くじ取らずで後祭の殿(しんがり)を務める。
天明の大火(1788)年に御神体である神功皇后の神面を残して焼失、その後再興されたものの、幕末の蛤御門の変(1864)による火災で鉾本体が焼失、以降は休み鉾となっていた。
近年になってお囃子や飾り席が復活し、宵山の際に一般に公開するようになり、2011年には唐櫃(からひつ)に御神体を収めて巡行に参加。
2014年には鉾の再建が完了、150年ぶりに巡行に本格復帰を果たした。
御神体の神功皇后が子供を身ごもった状態で戦に臨み、帰還後に無事応仁天皇を生んだ、というゆかりから、大船鉾も安産のご利益があるとされる。
宵山では安産お守りとして腹帯が授与される。
船鉾の神功皇后は鎧姿なのに対し、大船鉾の神功皇后は戦を終えているため狩衣姿となっている。
幾たびの火災を免れた神面は、江戸時代以前の作といわれる貴重なもの。
舳先の飾りは大金幣と龍頭の二つがあり、1年毎交互に使用している。
鬮(くじ)とらずとは…鬮(くじ)とりしきで、山鉾の巡行順番を決める行事が行われているが、鬮(くじ)とらずは巡行順番が決まっている山鉾の事。
サイズ:約直径12×高7.8cm
作者:加藤起楽作
----------
昭和50年 京都に生まれる
平成09年 静岡大学卒業
平成10年 京都府立陶工高等技術専門校成形科修了
平成11年 同校研究科修了
平成12年 京都市工業試験場陶磁器コース本科修了
平成12年 伊藤昇峰に師事
平成14年 田中香泉に師事
平成15年 如水陶画苑にて創作
令和04年 悠楽窯として開窯
----------
箱:化粧箱
【有料個別包装について】
個別包装(有料)をご希望の方は、カートを見るをクリックしてから「個別包装を希望する」にチェックを入れたのち、ご希望数を「数量」追加してください。
※下記商品は個別包装の対象外となります。扇子、色紙の包装をご希望の場合は、それぞれ有料箱・有料袋をお付けいたします。
- メール便配送商品
- 扇子(有料箱可/包装なし)
- 色紙(有料袋可/包装なし)
- 干支御題 関連商品
Share